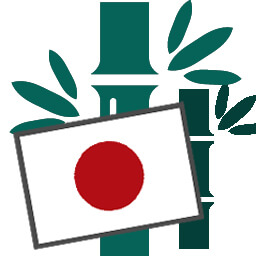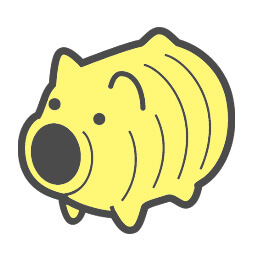
猫の目線から見た人間が描かれる。
今読んでもテンポも良く、新鮮で面白い。
人間観察が好きな人は、おすすめかも知れません。
わりと難しい語彙も使われていて、勉強にもなります。
『吾輩は猫である』の中で、人間はどんな風に書かれているのか、まとめました。
Contents
『吾輩は猫である』の”猫”から見た”人間”

『わが猫』の猫は自分を”ペルシア猫のような黄を含める淡灰色”だ、と言っていた。
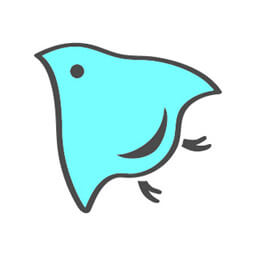
それは書生という人間中で一番獰悪な種族であったそうだ。
書生とは、勉強中の学生だ。
学生は獰悪な種族だという。無責任で羽目を外す様子は、今も昔も変わらないのかも知れません。
そして、この猫はその後、”書生は、ときどき猫を捕まえて煮て食う”と言ってますが。
獰猛という先入観からの、純粋な猫の受け取り方。
猫が幼児みたいで愛らしく感じる書き出しです。
漱石小説の中の教師像
教師というものは実に楽なものだ。人間と生れたら教師となるに限る。
漱石自身が教師だったせいもあり、小説に教師がよくでてきます。
猫から見た”教師”の姿は非常に楽に見えていた。
毎晩、大飯を食らい、胃薬を飲み、本を2、3ページ読んだら、そのまま眠りよだれをたらす。
猫から見た教師像、家の中での教師の様子。だらしないです。
ちなみに、漱石の別の作品『坊っちゃん』では、教師はこんな風に書かれてます。
考えてみるとやっかいな所へ来たもんだ。いったい中学の先生なんて、どこへ行っても、こんなものを相手にするなら気の毒なものだ。よく先生が品切れにならない。よっぽど辛抱強い朴念仁がなるんだろう。おれにはとうていやりきれない。
『坊っちゃん』より
無責任ないたずらをし、噓をついてごまかして、罰を逃げる。
認めることも謝ることもできない下劣根性の学生に対して、坊っちゃんが語る。
学生のことを、”話せない雑兵””腐った了見”だと、言ってのける坊っちゃん。
周りから見ると「教師は楽そう」
でも、当の本人からすると「やってられねえ」
なんでも、当の本人の気持ちと、まわりの人の感じ方は違うもんですね。
『わが猫』はやっぱ”猫”が主人公 猫本位で見た人間像はこんな感じ
吾輩は人間と同居して彼等を観察すればするほど、彼等は我儘なものだと断言せざるを得ないようになった。ー中略ー 人間ほど不人情なものはないと言っておらるる。
人間はわがままだ。
特に、子どもがわがままだという。
猫に対して、自分の気分で好きなことをする。猫を持ちあげたり、放り出したり、かまどの中に押し込んだり。
そして、自分に都合が悪くなったら、味方をつけ”家内総がかり”で猫に迫害を加える。
別の猫はまた、猫が子どもを出産すると、数日後に池のほとりに捨てに行くと訴える。
これぞ、人間原理主義的な考え方だ。
利己的、自己中、自分勝手。
自分本位の考え方の横行の危うさを、猫目線ながら漱石先生が斬る。
命がある限り、”人はこうなる”と言われているようだ。
人間が所有権という事を解していない。
あるいはこんな。
猫の世界では、”めざしの頭”でも”ぼらのへそ”でも、最初に見つけた者に食う権利がある。
この規約は暗黙の了解で、破ると、腕力に訴えてもいいという。
人間は、猫が見つけたものをすぐに略奪して、すましている。猫にとっては死活問題。
”いくら人間だって、そういつまでも栄える事もあるまい。まあ気を永く猫の時節を待つがよかろう。”と猫は吐き捨てる。
猫の思いなんぞ、つゆ知らず。
確かにそんな場面多く目にします。
人間といっしょに暮している猫は、どう感じているのでしょう。
人間からすれば、「エサ」を与えてるから、他のことは気にしないのかも知れませんが。
他人への親切は、相手が喜んでいこそ。
猫からすれば、自分で獲った獲物は自由にしたいでしょうね。
元来人間というものは自己の力量に慢じてみんな増長している。少し人間より強いものが出て来て窘めてやらなくてはこの先どこまで増長するか分らない。
昼寝をしていた猫。
他人に言われて影響を受けた主人が、猫を写生する。
猫から見ても、なんとも下手くそな絵だった。
目覚めた猫は、あくびがしたくなったが、主人が必死に描くので辛抱した。
しかし今度は、尿意をもよおし、我慢に我慢したが、我慢しきれずトイレに立った。
そこへ主人からの「この馬鹿野郎!」の一言。
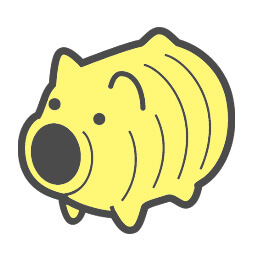
猫は、言葉が理解できない、何もわかっていないと思いこむと、人はこうなるのかも知れない。人間の慢心に猫が鳴らすアラート。漱石の小説がなければ、人が”客観視”するというスタンスは、生まれてこなかったかも知れない。
猫に言われてハッとする所もある。
でも、猫は猫本位で語っているので、人間も猫もどっちもどっちじゃん。って思う。
生き物の定めなんですね、本位主義って。
人間ほどふてえ奴は世の中にいねえぜ。
人間てものあ体の善い泥棒だぜ。
猫の獲ったネズミを勝手に取り上げて、交番に5銭で売りに行く人間に対して。
猫の気も知らず、猫からするとただの泥棒だと言う。
このくらい明瞭な事を分らずにかくまで苦心するかと思うと、少し人間が気の毒になる。
”このくらい明瞭な事”とは、絵葉書に描いてあった絵が、主人公である猫をモチーフに描いてあった事だなのだが。
その絵葉書を、主人が、縦から見たり横からみたりしながら、「うまい絵だなあ。でも何が描いてあるんだ?」と真剣に悩んでいたことに対して向けられた言葉だ。
猫に完全に馬鹿にされている様子。そして、猫は”吾輩が描いてあることはわからずとも、せめて猫の絵だということはわからせたい”と思いつつも。

人間というものは到底吾輩猫属の言語を解し得るくらいに天の恵に浴しておらん動物であるから、残念ながらそのままにしておいた。
と、主人をバサッと切り捨てる。
同じ人間ではあるが、なぜか猫に切り捨てられるさまが痛快に感じる場面である。
「吾輩は猫である」の中では、人間がさも愚鈍な生き物として描かれている。
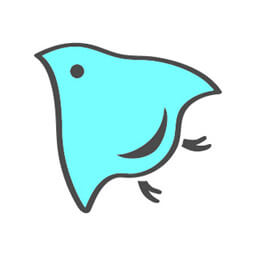
人間の眼はただ向上とか何とかいって、空ばかり見ているものだから、吾輩の性質は無論相貌の末を識別する事すら到底出来ぬのは気の毒だ。
自分の飼い猫の性格だけでなく、姿かたちの判別もできない人間。
まこと気の毒な生き物だという。
”向上心”などという、上向きな言葉をかっこつけて語ったりするから、人間は足元のことが見えないのだ、と。
人間は利己主義から割り出した公平という念は猫より優っているかも知れぬが、智慧はかえって猫より劣っているようだ。
人間は利己的だ。つまりわがままだという。
だから、”公平”という言葉を生み出した。
その辺は猫より賢いけど、知恵は猫に劣っているという。
何も顔のまずい例に特に吾輩を出さなくっても、よさそうなものだ。吾輩だって喜多床へ行って顔さえ剃って貰やあ、そんなに人間と異ったところはありゃしない。人間はこう自惚れているから困る。
「衣装は美しいが顔はまずい。まるでうちの猫のようだ。」という発言に対する猫の言葉。
わざわざ自分を不細工の例にあげるな、と。吾輩だって、理髪店にいって顔さえ剃ってもらえば、人間と変わらない。と断言する。
猫は、自分が毛深いから、不細工なだけで、顔そりさえすれば、人間と同じだ、うぬぼれるなよ。と言う。
おもしろすぎる猫の発言だ。
小説中の人間の名前をつけるに一日巴理を探険しなくてはならぬようでは随分手数のかかる話だ。
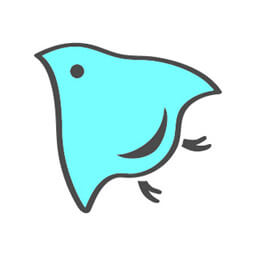
人間は自分よりほかに笑えるものが無いように思っているのは間違いである。吾輩が笑うのは鼻の孔を三角にして咽喉仏を震動させて笑うのだから人間にはわからぬはずである。
唯一笑うことができる生き物は”人間”である、という言葉への反論だ。
猫も笑うが、人間はその笑いに気づいていないのだと言う。
人間というものは時間を潰すために強いて口を運動させて、おかしくもない事を笑ったり、面白くもない事を嬉しがったりするほかに能もない者だと思った。
人間は、しゃべることに時間を費やす。
相手がしゃべってくることに対して、なぜ受け答えをしようとするのか。黙って聞いてりゃいいのに。だって、話しかけてきている相手は、あなたが普段文句を言っている人ででしょうに。
なぜ、それを顔に出さず、普通に会話ができるのか。
面白くもない会話がよく平気でできるもんだ、と猫は考える。
そう考えると、よけいに会話が面白くないものに聞こえてくるという。
感じ取り方は、幼児のようだが、目の前のことに対する考察は深く、なんだか人生哲学しているおっさんのようだ。
『わが猫』猫と人間の共通点

漱石と子規が住んだ”愚陀仏庵” 2010年7月の豪雨で全壊してしまった
三度以上繰返す時始めて習慣なる語を冠せられて、この行為が生活上の必要と進化するのもまた人間と相違はない。
1度したことは、2度やりたい。
2度試みたことは、3度目をやりたい。
この”心理的特権”を持っているのは、人間だけでなく猫も同じである、という。
だから、猫は、”金田邸”へ何度も何度も忍び込むのだった。
猫にとって、都合のよい事は、「この気持ち、人間だってわかるだろ?」と言わんばかりだ。
元来吾輩の考によると大空は万物を覆うため大地は万物を載せるために出来ている――いかに執拗な議論を好む人間でもこの事実を否定する訳には行くまい。さてこの大空大地を製造するために彼等人類はどのくらいの労力を費やしているかと云うと尺寸の手伝もしておらぬではないか。自分が製造しておらぬものを自分の所有と極める法はなかろう。自分の所有と極めても差し支えないが他の出入を禁ずる理由はあるまい。
地球上の自然は、人間が作ったものではない。
生き物として与えられているものだ。だから、自分のもののように取り扱うのはおかしいだろう。
と、猫は憤る。
猫も人間も、同じ地球の生命体だというもっともな意見である。
本を忘却するのは人間にさえありがちの事であるから猫には当然の事さと大目に見て貰いたい。
熱弁をふるった猫。
なぜ、熱弁をふるったのかを忘れてしまった言い訳をする。
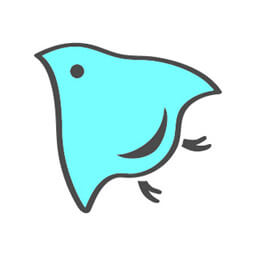
『わが猫』だんだん挑戦的になる吾輩の言葉

人間は贅沢なものだ。なまで食ってしかるべきものをわざわざ煮て見たり、焼いて見たり、酢に漬けて見たり、味噌をつけて見たり好んで余計な手数を懸けて御互に恐悦している。
人間は、料理して食べ物を食べる。
そして、それだけでなく、着物を着ている。
生き物として不完全だから、”羊の厄介になったり、蚕の世話になったり、綿畠の情けにあたる”と言う。
人間の”贅沢は無能の結果だ”と断言される。
なんだかだんだんと挑戦的な猫。
人間へのストレスが溜まってきているのだろう。
一羽飛ぶともういけない。真似をする点において蝉は人間に劣らぬくらい馬鹿である。
蝉に対する馬鹿発言。これまた、ひどい言いようだ。
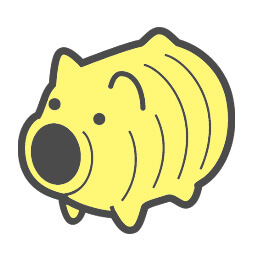
人間は愚なものであるから、猫なで声で――猫なで声は人間の吾輩に対して出す声だ。吾輩を目安にして考えれば猫なで声ではない、なでられ声である――よろしい、とにかく人間は愚なものであるから撫でられ声で膝の傍へ寄って行くと、大抵の場合において彼もしくは彼女を愛するものと誤解して、わが為すままに任せるのみか折々は頭さえ撫でてくれるものだ。
”人間は愚なものであるから”と猫が言う。
また挑戦的発言!?と言うよりも…、ここはそれが言いたいのではないだろう。この部分のメインは?
そう、”猫なで声”だ。
漱石先生、”猫なで声”は人間目線の言葉だから、猫から見ると”なでられ声”と、これが言いたいだけじゃねえのか~、と思ってしまう。
猫から見た人間の姿よりも、”猫なで声”の方に気が向く部分です。
主人はまた大きくなったなと思うたんびに、後ろから追手にせまられるような気がしてひやひやする。いかに空漠なる主人でもこの三令嬢が女であるくらいは心得ている。女である以上はどうにか片付けなくてはならんくらいも承知している。承知しているだけで片付ける手腕のない事も自覚している。そこで自分の子ながらも少しく持て余しているところである。持て余すくらいなら製造しなければいいのだが、そこが人間である。人間の定義を云うとほかに何にもない。ただ入らざる事を捏造して自ら苦しんでいる者だと云えば、それで充分だ。
子どもがいると、常に苦労がやってくるよね。
子どもを作って苦労する。
それが、人間の定義だと。
たしかに苦労はするけど、それを”定義づけ”てしまう発想が、漱石の言葉を生み出すのでしょうね。
『わが猫』 猫から人間へのアドバイスか!?
人間にせよ、動物にせよ、己を知るのは生涯の大事である。
人間が自分の身の程をしったならば、尊敬されてもいい、と猫は感じている。
今は、まだ人間は尊敬に値していないという見方である。
人間がそんなに情深い、思いやりのある動物であるとははなはだ受け取りにくい。
人間の嘆きや同情は、自然から沸きあがる感情ではない、と猫は見切っている。
人間は、さほど情け深く思いやりのある生き物としては映っていない。
気の毒な顔や涙は、”交際のため”にあるものだと言い、それは”骨の折れる芸術”だと形容する。
猫の淡白さが表れている。
人間といっしょに暮しているが、人間との距離はずいぶん遠く取っているのだろう。
『わが猫』 猫の最期
『吾輩は猫である』では、猫の最期が訪れる。
猫はビールを飲んで、酔っ払い、甕でおぼれて死んでしまう。
あっけない幕切れだが、猫は最期まで冷静に状況を分析する。
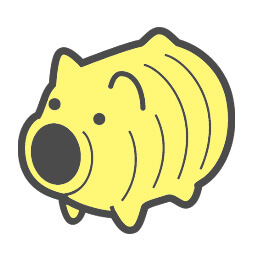
最期がくることを予感しての、”人間へのアドバイス”が小説の後半部分に出てきたのだろう。
『吾輩は猫である』の”猫”から見た”人間”の姿【漱石の見た景色】 まとめ
猫に鋭く、指摘される人間の生きざまは、同じ人間ながらに愉快でもある。
しかし、次第に猫の指摘は挑戦的になり、きつい言い方に、面白く感じない人もいるだろう。
だが、終盤では、人間に寄り添うような言い方にもなる。
だから、最後に猫が死にそうになるとき、「なんとか助けたい、助かってほしい」と思わされてしまう。
挑戦的な言い方の猫のままだと、「助かってほしい」とは思うまい。
この猫は、インテリジェンスを持っているので、そのまま静かにおぼれ死ぬ。
猫の最期をみると、これまでの猫の言葉がわりと素直に入ってくる。
これが、漱石の”カラクリ”か。
そういうことなんだろう。
猫目線だからおもしろい、というだけでもなさそうだ。
漱石の、人間に対する鋭い”洞察力”と、巧みな”表現力”、そして小説の構成における”カラクリ”があるから惹かれるんだわ。きっと。
この小説、初めは二十歳の頃に読んで、たしか猫の洞察力に驚いたっけ。
今読むと、語彙の学習にもなるくらい、たくさんの言葉を駆使して書いている。
夏目漱石『吾輩は猫である』
猫から見た人間の姿。
人間、今と昔と同じところ、いっぱいあるな~。
という、一考察でした。
おわり